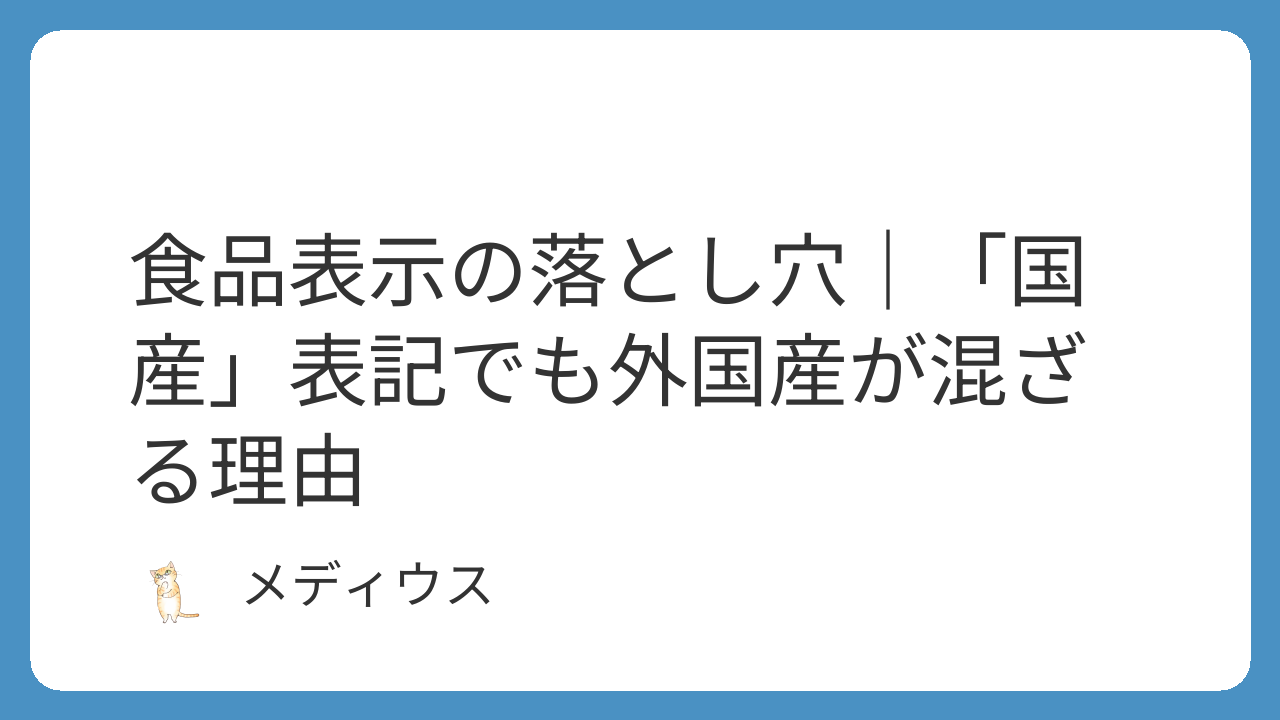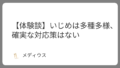10年以上前、スーパーで感じた違和感
2013年のある日。
テレビで輸入食品の危険性を取り上げる番組を見た。給料は少なかったが、家族の健康を考えて必ず国産を選ぶようにしていた。
スーパーに立ち寄ると、ブロッコリーが目に入った。米国産98円、国産298円。約3倍の価格差。にんにくは更に衝撃的で、中国産38円に対して国産は128円だった。
「日本産でもこのくらいの値段で買えたらなぁ」
そう思いながらも、外国産への不信感から絶対に買わなかった。そして厚生労働省の輸入食品監視統計を見て、私の不信感は確信に変わった。中国や米国からの輸入食品には、基準を超える添加物やカビ、菌が付着した違反事例が多数あったのだ。
しかし、もっと衝撃的な事実を知った。
「国産」と表示されている食品でも、外国産が混ざっている可能性があるということを。それが「50%ルール」と呼ばれる制度だった。
あれから12年。2025年の今、状況はどう変わったのか。
法改正はあったが、抜け穴は残った
2013年当時の衝撃:50%ルール
当時、私が知って驚愕したのが「50%ルール」だった。
例えば牛と豚の合挽きミンチの場合、牛51%(国産)豚49%(中国産)なら、原産国表示は「国産」でよかった。
ミックス野菜はもっと酷い。キャベツ40%(中国産)、レタス30%(日本産)、パプリカ30%(韓国産)の場合、50%を超える原材料がないため、原産国表示自体が不要だった。
「国産」と書いてあっても半分近く外国産が混ざっている可能性がある。この事実を知ったとき、私がいつも買い物をしているスーパーのミンチを思い出して気持ち悪くなった。
では、2022年の法改正でこの問題は解決したのか?
2022年4月、原料原産地表示が完全義務化
2017年9月に食品表示基準が改正され、2022年4月からは国内で製造される全ての加工食品について、重量割合上位1位の原材料の原産地表示が義務付けられた。
以前は一部の加工食品(22食品群と個別品目)だけだった表示義務が、全ての加工食品に拡大された形だ。
これで消費者は原産地を確認しやすくなったはず――そう思っていた。
しかし「又は表示」という新たな抜け穴
ところが、この法改正には大きな抜け穴があった。
「又は表示」という制度だ。
例えば、豚肉を使った加工食品の原材料表示に「豚肉(アメリカ産又はカナダ産又は国産)」と書かれていても、これは合法なのだ。
実際にどこの豚肉を使っているかは、製造時期によって変わる。「又は」で繋がれた表示は、過去の使用実績や今後の使用計画に基づいて、使用する可能性のある産地を全て列挙しているだけだ。
つまり、消費者は結局どこの豚肉を食べているのか分からない。
「大括り表示」で更に曖昧に
もっと曖昧なのが「大括り表示」だ。
3カ国以上の外国産を使う場合、「輸入」とだけ表示すればいい。例えば「豚肉(輸入)」という表示を見ても、それがアメリカなのか、ブラジルなのか、中国なのか、全く分からない。
「輸入又は国産」と書かれていれば、世界中のどこの豚肉が入っているかもしれないということだ。
こんな表示に、一体どんな意味があるのだろう。
輸入食品の違反は今も続いている
中国産食品の違反事例は2024年度170件
厚生労働省が公表した2024年度(2024年4月~2025年3月)の「輸入食品等の食品衛生法違反事例」を見ると、中国産食品の違反事例は170件で国別最多だった。
10年以上前の2013年、私が見た違反統計とさほど変わっていない。
| 違反品目 | 件数 | 主な違反内容 |
|---|---|---|
| 生鮮にんじん | 19件 | 基準値超の農薬(メピコートクロリド)検出 |
| 冷凍ブロッコリー | 複数件 | 大腸菌群検出 |
| ピーナッツ類 | 複数件 | 発がん性物質(アフラトキシン)検出 |
| 生鮮ねぎ・たまねぎ | 9件 | 殺虫剤(チアメトキサム)検出 |
生鮮にんじんから検出されたメピコートクロリドは、過剰摂取による腎臓や肝臓への影響が指摘されている。生鮮ねぎ・たまねぎから検出されたチアメトキサムは、マウス実験で肝細胞がんの増加が認められている物質だ。
中国産は本当に危険なのか?
公平を期すために書いておく。
厚生労働省によれば、2023年度の中国からの輸入食品の違反率は0.02%で、全輸出国における違反率0.03%より低い。約91万件の輸入届出に対して206件の違反だ。
つまり統計上は「中国産だから特別危険」とは言えない。
しかし、違反件数の絶対数が最も多いのは事実だ。そして違反した商品が市場に流通してから回収される事例も相次いでいる。スーパーや外食チェーンで知らないうちに口にしている可能性は十分にある。
価格差は円安でさらに拡大
2025年現在の価格比較
2013年当時と2025年現在の価格を比較してみよう。
ブロッコリー
- 2013年:米国産98円 vs 国産298円(約3倍)
- 2025年:天候により変動が大きいが、国産は158円~350円程度。一時期は300円超えも珍しくなかった。2026年から「指定野菜」に追加され、価格安定化が期待されている
にんにく
- 2013年:中国産38円 vs 国産128円(約3.4倍)
- 2025年:中国産1玉100円前後 vs 国産1玉180~350円(約2~3.5倍)
価格差の倍率は変わっていないが、絶対額は円安の影響もあり全体的に上昇している。
国産を選び続けることは、以前より経済的な負担が大きくなっている。
「好みの問題」という欺瞞
2013年、テレビで聞いた信じられない言葉
10年前、テレビに出ていた東大名誉教授の言葉を今でも覚えている。
原産国表示の優先順位について問われた教授はこう答えた。
「食品表示法の優先順位は、①安全性(アレルギー、保存方法など)、②健康増進面(カロリー、食塩量など)、③選択材料(好み)です。原産国表示は③にあたります」
つまり、原産国表示は単なる好みの問題だと。
テレビを見ていた私は「この人は一体何を言っているんだろう」と思った。
基準が違う、守らない国がある
もし全ての国が同じ基準で食品を生産しているなら、確かに好みの問題だろう。台湾産が好き、トルコ産が好き、という話になる。
しかし現実は違う。国によって基準が違い、基準があっても守らない国がある。
中国の日本向け輸出基準は厳しいと言われる。しかし厳しい基準があっても守らなければ意味がない。実際に違反件数は2013年も2024年も最多なのだから。
安全性の低い国の食品を避けるのは「好み」ではなく、自衛だ。
2025年、この認識は変わったのか
答えはノーだ。
今も変わらない自己防衛の必要性
加工食品の原材料をよく見る
- 「又は表示」がある商品は、実際の産地が特定できない
- 「輸入」「大括り表示」は、複数の外国産が混ざっている可能性
- 原材料名の最初に書かれているものが最も多く使われている原材料
中国産・米国産を避けたいなら
- 生鮮食品は国産表示のあるものを選ぶ
- 加工食品は原材料表示を確認し、曖昧な表示の商品は避ける
- 冷凍野菜は特に注意(輸入品が多い)
価格と安全のバランス
国産を選び続けるのは経済的に厳しい。私自身、給料は上がらないのに物価は上がり続けている。
しかし、安いものには理由がある。
全てを国産にする必要はないかもしれない。リスクの高い食品だけでも国産を選ぶ、という選択もある。
10年経っても変わらない本質
2013年:50%ルールで産地が分からない
2025年:「又は表示」で産地が分からない
形は変わった。しかし本質は同じだ。
2013年当時、私は50%ルールの存在を知って衝撃を受けた。「国産」と書いてあっても、実際には外国産が混ざっている可能性があった。
2022年の法改正で、全ての加工食品に原料原産地表示が義務化された。
しかし「又は表示」「大括り表示」という新たな抜け穴により、消費者が本当に知りたい情報は結局分からない。
むしろ「表示は義務化されました」という建前だけ整って、実態は何も変わっていないことに、より強い違和感を覚える。
「好みの問題」=「国は責任を持たない」
あの東大名誉教授が言った「好みの問題」という言葉は、裏を返せば「国は責任を持たない。自分で判断しろ」という意味だったのだろう。
ならば、私たちは自分で勉強して、自分で判断するしかない。
変わらないもの、変わったもの
変わらないもの
- 輸入食品の違反は続いている(中国産は2024年度も170件で最多)
- 表示制度には抜け穴がある
- 自己防衛が必要
変わったもの
- 価格差は円安で拡大
- 給料は上がらず、国産を選ぶ経済的負担が増加
- 「義務化された」という建前だけが整った
結局、自分で判断するしかない
2013年も、2025年も、そしてこれからも。
国は最低限の枠組みを作る。しかしそれは消費者を守るためというより、事業者が対応できる範囲での妥協の産物だ。
私たちは自分で勉強して、自分で判断するしかない。
この10年間、何も変わっていないことが分かった。ならば次の10年も、自分で考え続けるしかないのだろう。![]()