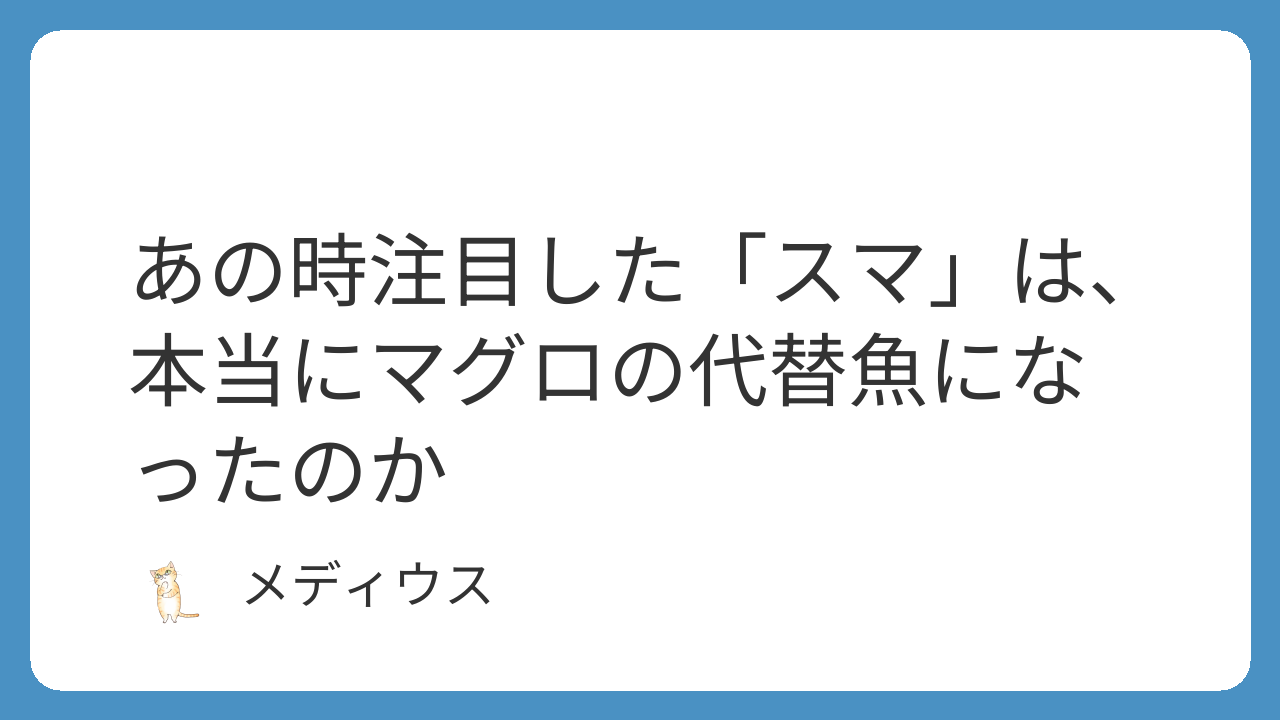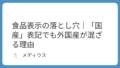2013年、ほとんど誰も知らなかった魚
当時の私の記事を読み返すと、スマについてこう説明している。
全長約1m、体重10kgほどのマグロの仲間。カツオとマグロの中間のような味で、あまり漁獲量が多くない希少な魚。

愛媛大学南予水産研究センターが完全養殖の研究を始めたばかりで、研究予算は驚きの280万円だった。
私は「個人的には未成魚のマグロより美味しいと思う」と書き、「早期の実用化を切に願う」と結んでいた。
正直、実用化できるのか半信半疑だった。成熟までに2年かかり、養殖のデータもほとんどない。商業化の目処は全く立っていなかった。
2025年、スマは完全に実用化されていた
結論から言うと、スマの完全養殖は大成功した。
2016年1月、愛媛県は世界で初めてスマの完全養殖出荷に成功した。研究開始からわずか3年後だ。近畿大学のクロマグロ完全養殖(2002年成功)と比べると驚異的なスピードである。
2020年には一般販売が開始され、「媛スマ(ひめスマ)」というブランド名で展開されている。トップブランドは「伊予の媛貴海(いよのひめたかみ)」。体重2.5kg以上、脂肪含有率25%以上(マグロの中トロに相当)という厳しい基準をクリアした最高級品だ。
現在、スマはふるさと納税の返礼品として、オンラインショップで、宅配寿司チェーンの期間限定メニューとして、全国どこからでも手に入る。かつて「幻の魚」と呼ばれたスマが、今やネットで買える時代になったのだ。
近大マグロと比べてどうなのか
スマの最大の強みは成長の早さだ。出荷までの期間は8ヶ月〜1年。近大マグロの約3年と比べると圧倒的に早い。
餌代も有利だ。クロマグロは1kg増やすのに14〜17kgの餌が必要だが、スマは小型マグロなので、クロマグロほど餌代はかからない。ちなみにブリは2.8kg、ノルウェーサーモンは1.2kgである。
味の評価も高い。「全身トロ」と評され、背は中トロ、腹は大トロ相当。臭みがなく、きめ細かな脂となめらかな口当たり。実際に食べた人の評価は非常に高い。
価格は養殖クロマグロと同程度かやや高い。2021年に宅配寿司チェーン「銀のさら」で期間限定販売された際は、補助金を活用して1貫290円(税抜)で提供された。これはスマの普及に向けた大きな一歩だった。
クロマグロの方はどうなったのか
一方、クロマグロの状況も劇的に変わった。
2010年、太平洋クロマグロの親魚資源量は初期資源量(漁業開始前)のわずか1.7%まで減少していた。絶滅が危惧されるレベルだった。しかし、2015年からの厳しい漁獲規制の結果、2022年には初期資源量の23.2%まで回復した。資源量は2010年の約10倍になったのだ。
これは国際協力による資源管理の大成功例である。
さらに2024年12月の国際会議で、2025年から漁獲枠の拡大が合意された。大型魚(30kg以上)は現在の1.5倍、小型魚(30kg未満)は1.1倍に増える。静岡の魚屋の社長は「本マグロの量が増えてくるから、今までみたいに貴重品ではなく、庶民的な価格になるかもしれない」と語っている。
クロマグロは、乱獲から回復へ。マグロ自体が「代替魚が必要なほど逼迫した状況」から脱しつつあるのだ。
予測は当たったのか?
私の2013年の予測を振り返ってみよう。
当たった部分
- スマの完全養殖は実用化された(2016年成功、2020年一般販売)
- 味は確かにマグロに匹敵する(「全身トロ」という評価)
- 養殖業のレパートリーになった(愛媛県の新しいブランド魚として定着)
予想外だった部分
- クロマグロ自体が回復した(当時は「減り続ける」前提だった)
- スマの成長が想定以上に早かった(8ヶ月〜1年で出荷可能)
- 近大マグロも普及が進んだ(完全養殖マグロが複数の選択肢に)
2013年の私は「代替魚」という言葉を使った。マグロが減るから代わりにスマを、という発想だった。
しかし2025年の現実は違った。スマは「マグロの代わり」ではなく、「スマという新しい高級魚」として確立された。マグロはマグロで資源が回復し、近大マグロも普及した。選択肢が増えたのだ。
| 項目 | 2013年の予測 | 2025年の現実 |
|---|---|---|
| スマ | マグロの代替魚になる | 独自の高級魚として確立 |
| クロマグロ | 減り続ける | 資源回復(2010年の10倍) |
| 近大マグロ | 実用化は不透明 | 年間752トン出荷 |
| 選択肢 | スマで代替 | 選択肢が増えた |
研究予算280万円の顛末
2013年当時、私は「研究予算が驚きの280万円」と書いた。
あれから12年、愛媛大学・愛媛県・生産者の産官学連携は見事に実を結んだ。完全養殖技術の確立、次世代育種システムの開発、大量生産技術の確立、ブランド化の成功、そして北米輸出への道筋まで。280万円から始まった研究が、愛媛県の新しい水産業を生み出した。
投資回収という意味では、大成功だろう。
12年間で分かったこと
この12年間で分かったことがある。
まず、資源管理は機能する。クロマグロの回復は、国際協力による資源管理が正しく機能すれば、魚は回復することを証明した。
次に、完全養殖は現実的な選択肢になった。近大マグロ、媛スマ、どちらも完全養殖に成功した。天然資源に頼らない水産業は、もはや夢物語ではない。
そして最も重要なのは、「代替」ではなく「多様化」だということ。スマはマグロの代替魚ではなく、新しい選択肢になった。これからの水産業は、「何かの代わり」ではなく、「新しい価値の創造」なのだろう。
地方大学の研究力も見逃せない。愛媛大学の研究は、近畿大学に匹敵する成果を出した。「近大マグロ」に続く「愛媛大スマ」。大学発の完全養殖魚が日本の水産業を変えつつある。
当時の記事の最後で、私はこう書いた。
「いつの世も天然物をとる漁師が注目を浴びがちだが、このように天然資源を減らさずになんとかしようとしている養殖漁師が私は好きだ」
この考えは今も変わらない。むしろ、クロマグロの回復と完全養殖の成功を見て、確信が強くなった。
持続可能な水産業は可能なのだ。
参考情報