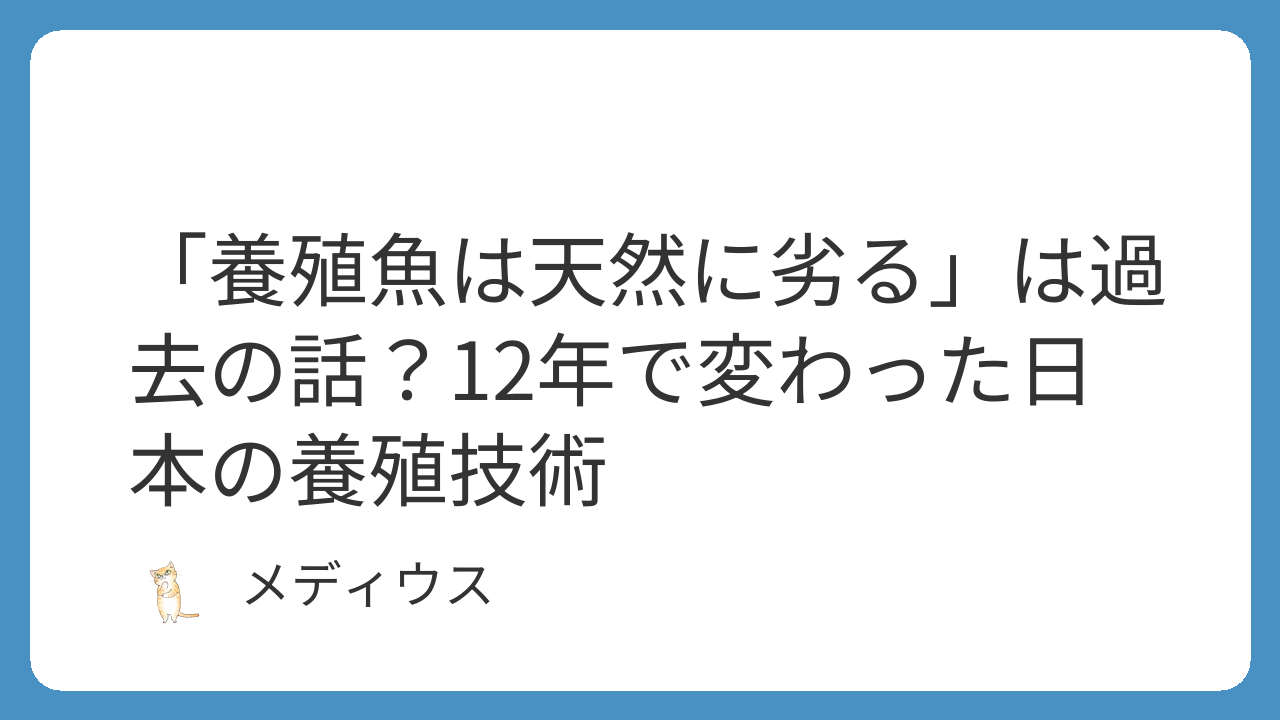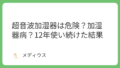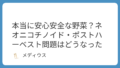2013年当時の状況を振り返る
12年前、私はこんな記事を書いていた。
フグといえば高級魚の代名詞。私のような下賤の者では食べられないと思い込んでいたのだが、調べてみると状況は違っていた。
養殖トラフグの実力(2013年時点)
天然トラフグの年間生産量が100トン程度だったのに対して、養殖トラフグの年間生産量は約4,000トン。値段は養殖物に比べて天然物の方が数倍~数十倍高かった。
しかし味はどうだったかというと──。
国産の養殖トラフグはクロマグロと並んで日本を代表する最先端の養殖技術の結晶。味や食感では天然を超えたといわれている
近畿大学の有路昌彦准教授がこう言っていた。天然を超えたは言い過ぎかもしれないが、かなりのレベルだったのだろう。
当時の私は気づき始めていた。日本の養殖技術は非常に高く、近大のマグロを筆頭にブリ(ハマチ)やマダイ、スマ等数多くの魚種を養殖している。
「養殖物は天然物には敵わない」という考えは既に過去のものなのかもしれない──そう思い始めた。
ハマチ養殖の変化(2013年時点)
当時の私はハマチについて調べていた。
私はハマチ養殖について、沿岸に網で囲った生簀を作り、密集された中で餌を与え養殖するというイメージを持っていた。狭くて汚い水の中で養殖するので餌臭くてすぐに病気になるから抗生物質漬けだろうと。
しかし実際は違った。
2013年時点で既に、潮の流れが速くて海水が循環する外海に筏を係留する方法が主流になっていた。
潮の流れが速い外海で養殖する事によって、以下のようなメリットがあり、天然物と比べても遜色ない味のハマチが提供できるようになっていた。
- 餌が海底に沈殿する事も防げる
- 水質が悪くなりにくいので抗生物質の投与も減る
- 魚の運動量も増える
時期によっては天然物をはるかに上回る味なので、天然物よりも養殖物の浜値(港で取引される値段)が良いという逆転現象まで起きていた。
2013年の私の結論
当時、私は記事をこう締めくくっていた。
味に関しては好みもあるので養殖物が最高とは言えないし、ブランド力でも天然物の方がいいという人の方が多いとは思うが、そろそろ養殖物についての間違った偏見は捨てるべきかもしれない。
それから12年:何が変わったのか
近大マグロの光と影
2013年、近大マグロは希望の星だった。2002年に世界初の完全養殖に成功し、2010年から豊田通商と組んで量産化事業を開始。2014年には2020年に年間30万尾の稚魚を生産する計画を発表していた。
しかし2025年、状況は一変した。
マルハニチロは完全養殖クロマグロの生産を8割削減。ニッスイや極洋など大手水産会社も撤退。近大マグロの稚魚の出荷は近年ほとんど実績がなくなってきている。
なぜ失速したのか
理由は明確だ。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 餌代高騰 | マグロは1kg太るのに15kgの餌が必要。天然のサバやイワシの不漁で餌代が高騰 |
| 天然資源回復 | 2025年の日本近海における漁獲枠の拡大で天然マグロの供給が増加 |
| 長期育成 | 出荷まで5年かかる。通常の畜養マグロ(天然稚魚から3~4年)より長い |
| 採算悪化 | 餌代高騰と市場価格の安定化で収益性が大幅に悪化 |
技術的には成功していた。しかしビジネスとして成立しなかった。
近大は「完全養殖技術の研究は続ける」としているが、商業生産はほぼ消滅する見通しだ。
サーモン養殖の大躍進
近大マグロが失速する一方で、国内のサーモン養殖は大きく成長した。
2013年と2025年の比較
| 項目 | 2013年 | 2025年 |
|---|---|---|
| 国内生産量 | ほぼゼロ | 約7,000トン(推定) |
| 主な生産者 | なし | 日本サーモンファーム、ニッスイ他 |
| 消費量 | 約32万トン | 約33万トン |
| 輸入依存度 | 約85% | 約80% |
日本サーモンファームは2015年に青森県で大規模養殖を開始。2025年には3,500トン、ニッスイは3,400トンを出荷予定。5年で生産量を3.4倍にする計画だ。
なぜサーモンは成功したのか
- 回転寿司で一番の人気ネタ
- 若年層の嗜好性が高い
- 市況が堅調に推移
- 技術移転が比較的容易(北欧のノウハウ)
マグロとサーモン。同じ「人気の魚」でも、明暗が分かれた。
ブリ養殖の安定成長
日本で最も多く養殖されている魚類はブリだ。
2022年のブリ生産データ
| 項目 | 生産量 |
|---|---|
| 養殖ブリ類 | 113,700トン |
| (内訳)ブリ | 84,400トン |
| (内訳)カンパチ | 24,800トン |
| (内訳)ヒラマサ | 4,500トン |
| 天然ブリ類 | 92,800トン |
養殖が天然を上回っている。
主な産地は鹿児島県(37,260トン)、愛媛県(17,091トン)、大分県(16,521トン)。九州・四国地方が全国の約76%を占める。
ブリ養殖の現状
1928年に香川県で始まったブリ養殖は、90年以上の歴史がある。2013年当時から既に技術は成熟していたが、2025年も安定した生産が続いている。
派手な技術革新はない。しかし着実に品質を向上させ、市場に供給し続けている。これが日本の養殖業の底力だ。
ゲノム編集魚の登場
2021年、養殖魚の世界に革命が起きた。
リージョナルフィッシュ(京都市)が開発したゲノム編集マダイとゲノム編集トラフグが、厚生労働省と農林水産省への届け出を受理され、販売が開始された。
ゲノム編集とは何か
生物がもともと持つ遺伝子を働かなくする技術。外来遺伝子を導入する「遺伝子組み換え」とは異なる。
肉厚マダイ
- 筋肉の形成を抑える遺伝子(ミオスタチン)を働かなくした
- 可食部の筋肉量が1.2~1.6倍に増加
- 飼料利用効率が14%改善
- 2021年9月、クラウドファンディングで320万円を調達
高成長トラフグ
- 食欲抑制ホルモン(レプチン)の受容体をつくる遺伝子を働かなくした
- 通常の約2倍に成長
- 飼育期間の短縮が可能
世界初の快挙、しかし…
日本は世界で初めてゲノム編集動物食品を実用化した。
これは快挙だ。しかし同時に、不安の声も大きい。
安全性は確認されたとされているが、長期的な影響は未知数。表示義務もない。京都府宮津市では市民が反対署名を提出(1万661筆)するなど、社会的な受け入れはまだ難しい状況にある。
陸上養殖の課題
ゲノム編集魚は陸上養殖で育てられる。海への流出を防ぐためだ。
しかし陸上養殖には大きな課題がある。
電気代の壁
水産庁の実験によると、トラフグの陸上養殖はランニングコストの約6割を電気料金が占め、飼料費の3倍に達する。
日本の電気料金はノルウェーの約3倍。最大コストの電気料金に大きな格差がある状況で国際市場で競争できるかは不透明だ。
かつて日本のアルミニウム精錬は「電気の缶詰」と呼ばれ、電気料金格差で2014年に消失した。陸上養殖も同じ道を辿る可能性がある。
2013年と2025年:何が変わり、何が変わらなかったか
変わったこと
| 項目 | 変化 |
|---|---|
| 技術革新 | ゲノム編集、陸上養殖など新技術が登場 |
| サーモン | 国内養殖がほぼゼロから7,000トンに成長 |
| 近大マグロ | 期待の星から商業生産ほぼ消滅へ |
| SDGs意識 | 持続可能性が重要な判断基準に |
| 消費者意識 | 「養殖=劣る」から「養殖=安定品質」へ変化(一部で) |
変わらなかったこと
| 項目 | 現状 |
|---|---|
| 偏見 | 「養殖は天然に劣る」という偏見は依然として根強い |
| ブリ | 安定生産を続けているが、派手な話題はない |
| マダイ | 高品質な養殖が継続 |
| 経営環境 | 小規模経営、高齢化、輸入品との競争など課題は同じ |
| 本質 | 丁寧な飼育管理と品質管理こそが重要 |
2025年の私の結論
主要養殖魚の生産量
| 魚種 | 養殖生産量 | 天然漁獲量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ブリ類 | 113,700トン | 92,800トン | 養殖が天然を上回る |
| サーモン | 約7,000トン | – | 国内養殖が急成長 |
| マダイ | データ非公開 | – | ゲノム編集品種も登場 |
| トラフグ | 4,000トン程度 | 100トン程度 | 養殖が圧倒的 |
| マグロ(完全養殖) | ほぼ消滅 | – | 商業生産は事実上終了 |
※2022-2023年データを基に作成
2013年、私は「養殖物についての間違った偏見は捨てるべき」と書いた。2025年になってもその思いは変わらない。
技術は進化した。ゲノム編集魚が登場し、サーモンの国内養殖が始まり、近大マグロは商業的には失敗した。しかし本質は変わっていない。
養殖魚は「劣った代替品」ではない。適切に管理され、丁寧に育てられた養殖魚は、天然魚に劣らない品質を持つ。ブリやハマチのように、時には天然を上回る。
12年前には想像もしなかった視点が加わった。それはサステナビリティ(持続可能性)だ。
天然資源は有限だ。乱獲は資源の枯渇を招く。養殖はこの問題への一つの答えになり得る。しかし近大マグロが示したように、技術的に可能でも経済的に成立しなければ続かない。サーモンが成功し、マグロが失敗した理由はここにある。
完璧な答えはない。
ゲノム編集魚には不安もある。陸上養殖にはコストの壁がある。しかし日本の養殖技術は90年以上の歴史があり、確実に進化してきた。
できない理由を探すより、できる方法を探す。それが養殖業者たちが90年以上続けてきたことだ。
養殖魚は、もう「安いから仕方なく食べるもの」ではない。「選んで食べるもの」になった。少なくとも、偏見で判断するのはやめよう。食べて、判断しよう。
それが12年前と変わらない、私の結論だ。