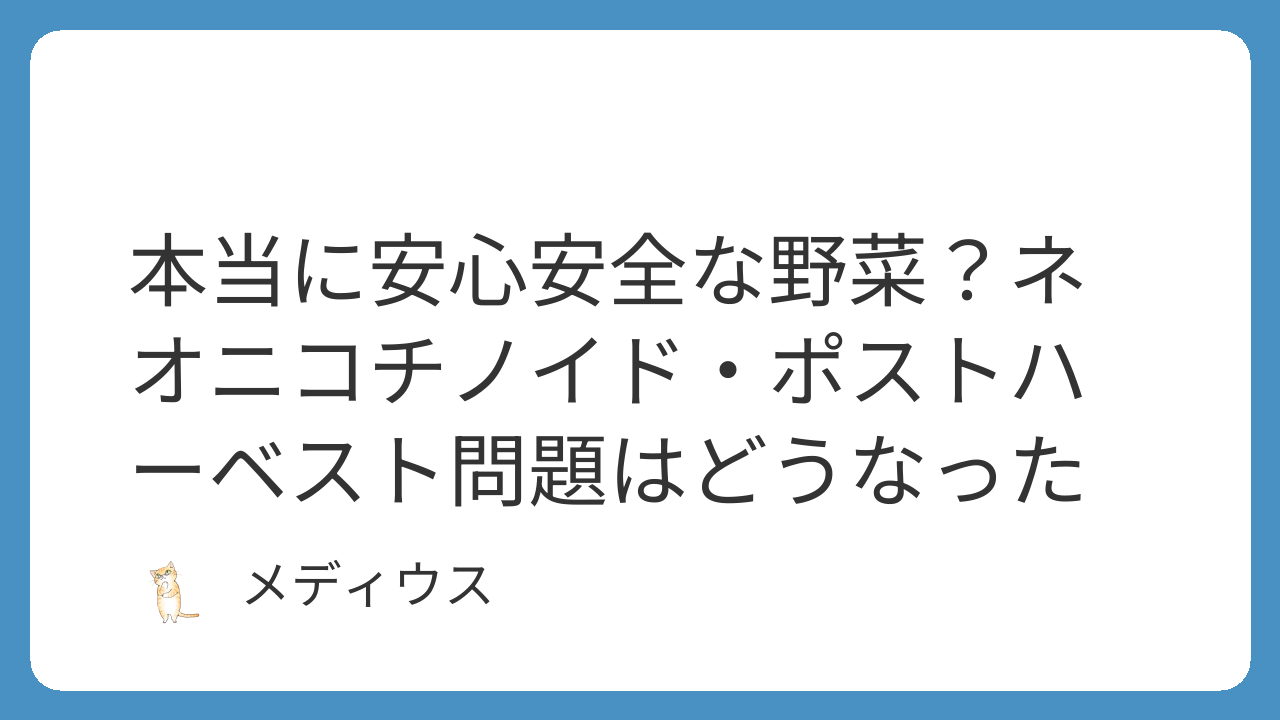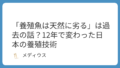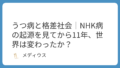2014年当時、私が心配していたこと
2014年当時、私が調べて分かったことはこうだった。
ネオニコチノイド系農薬の懸念
- ミツバチの大量死(蜂群崩壊症候群・CCD)の原因として疑われていた
- EUの専門機関(EFSA)が「人間の発達中の神経系統に影響を及ぼす可能性がある」と報告
- 昆虫の神経伝達物質を攪乱する仕組みは人間にも通用する可能性があった
- しかし日本の残留基準値はEUに比べて大幅に緩かった(例:キャベツで約100倍)
ポストハーベスト農薬
- 海外から輸入される果物や穀物に、腐らないよう薬剤を散布
- 枯葉剤と同じ成分を含むものもあった
- ガンの発生率を高めたり、遺伝子異常を引き起こす可能性が指摘されていた
- 日本では禁止だが、輸入品には使用されていた
無農薬論争
- 近畿大学の研究で「無農薬野菜の方が危険」という説が登場
- しかし私は大地を守る会の反論に同意していた
- 植物が本来持っている防御機能を「危険」とするのはおかしい
当時の私の結論は、「子供には食べさせたくない」だった。
それから11年:世界・日本はどう変わった?
ネオニコチノイド:EUは禁止、日本は?
2018年4月、転換点が訪れた。
EUがネオニコチノイド系農薬3種(クロチアニジン、イミダクロプリド、チアメトキサム)の屋外使用を全面禁止にしたのだ。ミツバチへの悪影響が科学的に確認されたためだった。
その後もEUは規制を強化し続けている。2023年9月には、クロチアニジンとチアメトキサムの残留基準値を大幅に引き下げ、事実上の「全面排除」に向けて動き出した。
では日本は?
残念ながら、逆方向に進んでいる。
2015年から日本ではネオニコチノイド系農薬の残留基準値が緩和され続けている。例えば、カブの葉におけるクロチアニジンの残留基準値はEUの2,000倍の40ppm、アセタミプリドの残留基準値ではEU基準の600倍というものもある。
科学的知見も進んだ。
獨協医科大学の研究チームが2009年前後に生まれた極低出生体重児の尿を分析したところ、生後48時間以内の検体の25%からアセタミプリドの代謝物を検出した。研究チームは、ネオニコチノイドが母親の胎盤をすり抜けて胎児の発育に影響を与えている可能性を示唆している。
2024年5月、米国シカゴで開催された「Silent Spring 2.0」会議では、最近の動物研究で、一部のネオニコチノイドに関する米国環境保護庁(EPA)の現在の安全基準が、実際に人々の安全を守れる数値より160倍も高い可能性が示唆された。
2014年の私の懸念は、的中していた。
対比される日本と世界
| 項目 | EU・欧米 | 日本 |
|---|---|---|
| ネオニコチノイド | 2018年から屋外使用禁止。残留基準値も厳格化 | 2015年から残留基準値を緩和。使用は継続 |
| アセタミプリド残留基準 | 厳格 | EUの最大600倍 |
| クロチアニジン残留基準 | 厳格 | EUの最大2,000倍(カブの葉) |
| 基本姿勢 | 予防原則(危険性が疑われたら規制) | 科学的証明後に対応(証明されるまで使用継続) |
新たな問題:グリホサート
2014年以降、新たな農薬問題も登場した。それが除草剤「ラウンドアップ」の主成分、グリホサートだ。
世界の動き
2015年3月、WHO(世界保健機関)の専門機関IARC(国際がん研究機関)が、グリホサートを発がん物質「2A」(おそらく発がん性がある)にランクした。
これを受けて世界では多くの国が規制に動き、フランスでは除草剤ラウンドアップと関連商品の販売を禁止した。
日本の対応
しかし日本では、2016年7月に内閣府の食品安全委員会がグリホサートの発がん性および遺伝毒性は認められないとの判断を示し、2017年12月には厚生労働省がグリホサートの食品残留基準を大幅に緩和した。
例えば小麦では現行の5〜150倍に緩和された。
賛否両論
ただし公平に言えば、グリホサートについては評価が分かれている。日本、米国、EUなどの主要国の安全性評価機関は、グリホサートに発がん性はなく、表示どおりに使用される限り安全であると繰り返し結論づけている。
世界の規制機関はグリホサートの「リスク」(実際の危険性)を評価し「発がん性は無い」と判断している一方、IARCは「ハザード」(潜在的な有害性)の評価を行っているという違いもある。
しかし、世界的には規制強化の流れがあるのは事実だ。
有機農業:成長する世界、伸び悩む日本
11年間で、有機農業市場は大きく成長した。
世界の有機農業市場
2024年、世界の有機農業セクターの有機管理下の土地面積は9,800万ヘクタールを超え、2022年の世界の有機市場の売上高は1,350億ユーロ(約22兆円)に達した。2024年の市場規模は1,715億ドル、2032年には2,873億ドルに成長すると予測されている。
日本の現状
日本の有機農業の面積は2022年8月現在で3万haで、耕地面積に占める割合はわずか0.7%だった。
日本の有機食品市場は2009年の1,300億円が2017年に1,850億円となり、過去8年で約4割拡大したものの、1人あたりの年間有機食品消費額は世界平均が1,638円に対して日本は1,408円。
ちなみに、スイスは3万9,000円、フランスは1万7,000円、米国は1万5,000円。日本は先進国の中で最低レベルだ。
ただし、日本の有機食品市場は2024年から2032年の間に年率9.7〜11.2%という高い成長率が予測されているので、今後の伸びには期待できる。
成功事例:佐渡島
JA佐渡は2015年にネオニコチノイド系農薬の米作向け販売を中止し、2018年からはネオニコチノイド系農薬不使用の米のみを販売している。トキの放鳥という明確な目標があったことで、地域全体が動いた成功事例だ。
ポストハーベスト農薬の現状
ポストハーベスト農薬については、11年経っても状況はほとんど変わっていない。
輸入農産物には今も使用されており、日本の検査はあるものの、すり抜ける事例も後を絶たない。
2025年版:私たちにできること
11年前、私は「子供には食べさせたくない」と書いた。
2025年の今、その思いはさらに強くなった。
世界が規制強化に動く中、日本は規制緩和を続けている。この「逆行」を前に、私たちにできることは何か?
選択肢1:有機野菜を選ぶ
値段は高いが、健康への投資と考える。大手スーパーでも有機野菜コーナーが増えてきた。
- イオン、イトーヨーカドー、コープなど大手スーパーの有機コーナー
- らでぃっしゅぼーや、大地を守る会、オイシックスなどの宅配サービス
- 地域の直売所(農家が直接販売)
選択肢2:生産者を選ぶ
有機認証を受けていなくても、農薬を減らす努力をしている農家は多い。
- 道の駅や農産物直売所で生産者の顔が見える野菜を買う
- 地域のCSA(地域支援型農業)に参加する
選択肢3:洗い方を工夫する
完璧ではないが、少しでも残留農薬を減らす。
- 流水で30秒以上よく洗う
- 外葉は捨てる
- 皮をむく(皮の栄養は失われるが)
ただし、ネオニコチノイド系農薬は浸透移行性(根や葉から吸収され、植物全体が殺虫効果を持つ)が高いため、洗っても落とすことができないことは覚えておきたい。
選択肢4:国産を優先する
ポストハーベスト農薬の心配がない。ただし、ネオニコチノイドなど他の農薬の問題は残る。
最も重要なこと:知ること、そして声をあげること
「農薬等を気にしていたら食べる物が無くなるよ」——11年前もそう言われた。
しかし、私は今も思う。ただちに影響がなくても、家族には食べさせたくない。
日本の食べ物は安心・安全と思いがちだが、日本の農薬規制は世界各国より緩いものが多く、国内向けの基準でつくった作物が、輸出先国の基準を満たせないケースも少なくない。
この事実を、もっと多くの人に知ってほしい。
2025年版の結論
11年前、私は野菜の安全性について疑問を持った。
2025年の今、その疑問は確信に変わった。日本の野菜は世界基準で見れば「安全」とは言えない。
しかし、絶望する必要はない。
私たち消費者には選択する力がある。高くても有機野菜を買う、生産者を選ぶ、地域のCSAに参加する、自分で育てる。
そして何より、このような問題を知り、周りに伝え、声をあげ続けること。健康でいられるようにと食べている野菜で、不健康にならないために。![]()