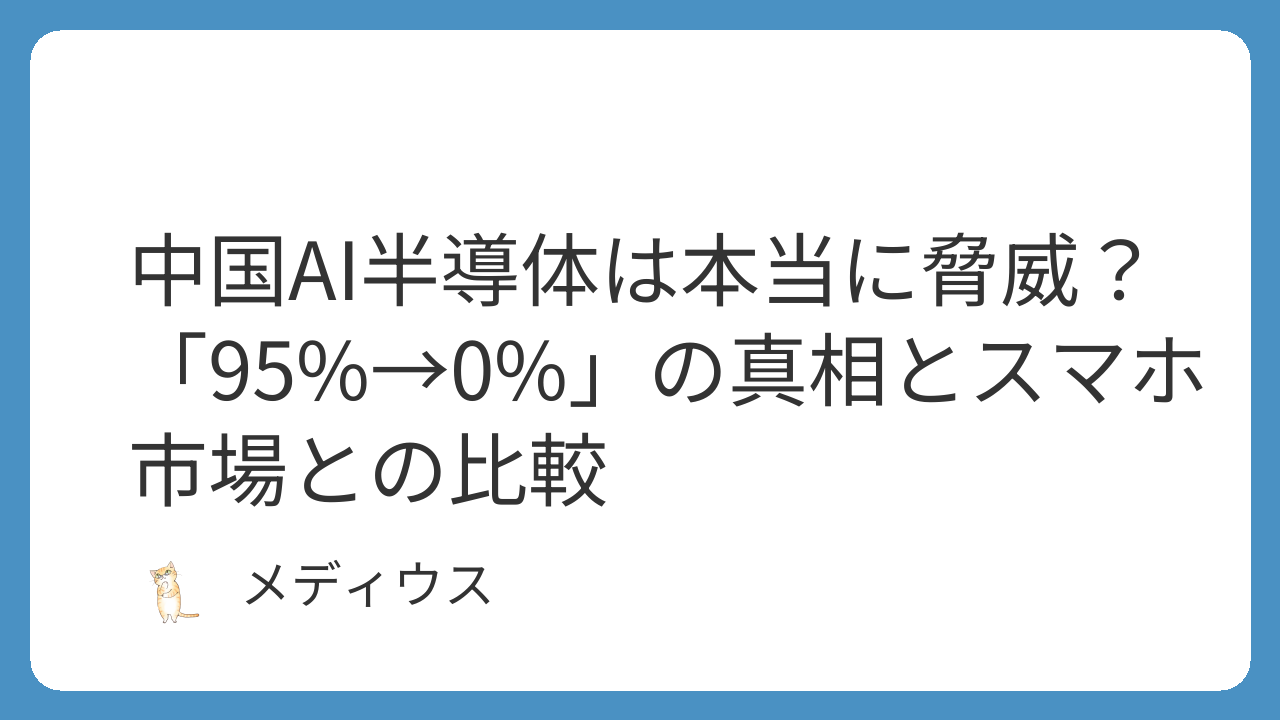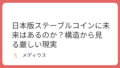2025年10月、エヌビディアのジェンスン・フアンCEOが衝撃的な発言をした。
「我々の中国市場でのシェアが95%から0%に急落した」
同じ頃、中国のAI半導体企業カンブリコンの株価が1年で5倍に跳ね上がり、売上が前年比43倍にまで伸びたという記事を見た。
「中国がAIで米国に追いつく」「脱エヌビディア達成か?」とメディアは騒いでいる。しかし、本当にそうなのだろうか。
気になって調べてみると、話は全然違った。
個人的には現在注目されている「中国AI脅威論」の多くは過大評価だ。 しかし同時に、10年後に後悔するかもしれない現実も見えてきた。
「95%→0%」の本当の意味
まず、エヌビディアCEOの発言を正確に理解しよう。
「シェアが95%から0%になった」
この発言自体は事実だ。しかし一体何のシェアなのだろうか?
2024年時点の中国AI市場シェアは以下の通りだ。
- エヌビディア:66%
- ファーウェイ:23%
- AMD:5%
- カンブリコン:1%
これがいきなりゼロになるわけがない。答えは簡単だ。これは「新しく売れなくなった」という意味なのだ。
2025年4月、トランプ政権がエヌビディアの対中輸出を事実上禁止した。その後、部分的に再開されたが、米中両政府の規制で新規販売はほぼゼロになった。
しかし、2022年から2024年に中国が買った数百万個のエヌビディアGPUは、まだ動いている。
在庫を使い切るまでは問題は表面化しない。では、いつ本当にゼロになるのか。
GPUの寿命は3〜5年だ。技術の進化も速い。2年前の最先端チップは、もう時代遅れだ。つまり、このままエヌビディアの輸出が途絶えたままなら、2027年から2030年頃に中国でのシェアは本当にゼロになるということだ。
「95%→0%」は確かに事実。しかし、その影響が出るのは数年先の話なのだ。
そして、その時までに国産チップがエヌビディアの代わりになっていなければ、おそらく中国のAI開発はかなり困難な状況に陥るだろう。
エヌビディアCEOの本音
ここで、冷静に考えてみよう。
エヌビディアCEOが「中国市場でシェアが0%になった」と公言したのは、本当に「中国の脅威」を警告するためだったのか。
私はそうは思わない。彼には別の動機がある。
エヌビディアにとって中国は巨大市場だった。2024年、中国での売上は170億ドルを超えた。これは総売上の約20〜25%にあたる。
しかし輸出規制で、その収益が消えた。2025年4月、対中輸出が禁止された時、エヌビディアは55億ドルの損失を計上した。
そして、5月、彼は公の場で言った。
「チップ規制は米国の競争力を損なう」「中国は強い」「中国がAIで勝つ」と。
その真意は明白だ。
- 「中国は強い」→ だから規制を緩和すべきだ。
- 「米国の競争力が落ちる」→ 政府よ、考え直せ。
そして、実際に効果があった。
2025年7月、米国政府は輸出を部分的に再開した。条件は、エヌビディアが中国での売上の15%を米国政府に納めることだった。
つまり、CEOの「中国脅威論」には自社製品を売りたいという思惑があるのだ。
彼は中国を過大評価することで米国政府に規制緩和を促している。これを理解せずに「CEOが言ってるから中国は強い」と受け取るのは素直すぎる。
中国のエヌビディアと言われる「カンブリコン」の実態
次に、カンブリコンの「急成長」を見てみよう。
- 2025年上半期の売上:前年比43倍
- 株価:1年で5倍
- 性能:エヌビディアの80〜90%で、価格は30%安い
こう見ると、確かに印象的な数字だ。
2024年時点では市場シェアはわずか1%、エヌビディアの66分の1で4位に過ぎなかった。しかし状況は急速に変わりつつある。
2025年上半期、営業キャッシュフローは前年同期の6億元のマイナスから9億元のプラスに転換した。通信、金融、インターネット業界で大量採用が進み、大規模言語モデル開発企業や高性能サーバーメーカーでの本格活用が始まっているとのことだ。
ただし、これを手放しで「脅威」と呼ぶのは早計だと思う。
なぜなら、この成長の大部分は以下の理由によるものが大きいからだ。
- 政府の強制的な国産化政策による需要
- エヌビディアが買えなくなったことによる「消去法」の選択
- 顧客基盤はまだ脆弱(上位数社に集中)
つまり、カンブリコンの爆発的な成長は「市場競争力」ではなく「環境変化」によるものだからだ。
とはいえ、この急成長が続けば、2〜3年後には市場構造が大きく変わっている可能性はある。これが、「過大評価」と「油断禁物」の両方が真実である理由だ。
中国が超えられない4つの壁
さらに深刻なのは、中国が直面している構造的な問題だ。私は「4つの壁」があると思う。
第一の壁:ソフトウェア(CUDA)
エヌビディアの本当の強さは、ハードではない。ソフトだ。
「CUDA(クーダ)」という、圧倒的な優位性を持つプログラミング環境が事実上の世界標準になっている。
- 3,000万回以上ダウンロード
- 300万人以上の開発者
- 世界のAI開発者の98%が依存
- 20年かけて構築された
2006年、エヌビディアは大きな賭けに出た。GPUを計算にも使えるようにするために巨額を投資してCUDAを開発したのだ。
当時は馬鹿げた投資に見えたが、2012年にAIブームが来た時、CUDAは標準になっていた。
すべての主要AIツールがCUDAのために作られ、開発者は何千時間もCUDAで仕事をし、企業は膨大なCUDAで書かれたコードを持っている。
この「20年の蓄積」はカネでは買えない。
中国はどうしているかというと、例えばファーウェイは独自のプラットフォームを開発し、既存コードの移植を簡単にしようとしている。
しかし、現時点では性能、機能、使いやすさ、すべてで劣る。
中国政府は、この状況を打破するために、強制的に開発者を国産ツールに移行させている。これは短期的には機能するかもしれない。
しかし、仕事の遅延、既存のコードの書き直し、世界の研究コミュニティからの孤立、など大きな代償がある。
CUDAの存在は、最も高く、強大な、まさに「難攻不落の要塞」なのだ。
第二の壁:メモリ
次に、「メモリ」の問題がある。
AIチップの性能はプロセッサだけでは決まらない。メモリの量と速度が実際の処理速度を左右する。
そして高性能メモリ(HBM)市場は、韓国企業が90%以上を占めている。
- SKハイニックス:約50%
- サムスン:約40%
- その他:約10%
- 中国:ほぼゼロ
ファーウェイの最新チップでさえ、2世代遅れたメモリを使っている。これはエヌビディアの3分の2の容量、40%の速度しかない。
ファーウェイは独自メモリを2026年に投入予定だが、専門家は「まだサムスンやSKハイニックスには及ばない」と言う。
チップがどれだけ優れていても、メモリが足を引っ張れば意味がないというわけだ。
第三の壁:製造装置
メモリ以上に深刻なのが「製造装置」だ。
最先端チップ(5nm以下)を作るには、オランダ企業ASMLだけが作れる特殊な機械が必要不可欠なのだが、米国の圧力によって中国への輸出が止まっている。
さらに、半導体製造に必要な機械のほとんどが米国・日本製で、すべて輸出規制の対象となっている。
結果、中国は2026年まで7nmプロセスに制限される見込みだ。対して、エヌビディアは5nm、そして3nmへ、さらなる高みへと着々と進んでいる。
7nmの檻に閉じ込められた状態で、どうやって5nm、3nmのチップと競争するのだろう。
第四の壁:地政学的孤立
ここで根本的な問いを発したい。もし中国が米国とだけ対立していたら、どうなっていただろうか。
- 台湾から最先端チップを買える
- オランダから製造装置を買える
- 韓国から最新メモリを買える
- 日本から材料を買える
この場合、ハードの問題はほぼ解決する。残る課題はソフトだけ。数年で何とかなったかもしれない。
しかし現実は違う。
すべての重要技術へのアクセスが同時に遮断されている。それは、中国は単なる競争相手ではなく、「体制の敵」と見なされているからだ。
民主主義 vs 権威主義。自由市場 vs 国家統制。人権 vs 社会管理。
さらに台湾問題、南シナ海、ウイグル・香港。これらが重なり、西側諸国は団結した。中国は西側技術同盟に包囲されている。
これは技術の問題ではない。イデオロギーと地政学の問題なのだ。
10年前のスマホは教訓になるか?
「なんだ、中国の脅威は誇張だったのか。安心した」
中国が超えるべき高くて険しいたくさんの壁の存在を知れば、多くの人はこう思うだろう。
しかし、例えば2014年当時の中国のスマートフォンはどう評価されていたか。
「安かろう悪かろう」「iPhoneのパクリ」「技術力0」
そして専門家は断言した。
「中国企業がアップルやサムスンに追いつくことはない。技術が違う。ブランドが違う。全てが違いすぎる」と。
しかし、2024時点の世界のスマホ市場シェアは以下のようになっている。
- アップル:17%
- サムスン:19%
- 中国勢合計(シャオミ、オッポ、ビボ、ファーウェイ等):40%超
中国企業は、追い越したわけではない。しかし、市場を分割した。
欧米・日本ではiPhoneやGalaxyが優勢、中国では中国勢が支配的な存在に、そして途上国では価格で中国勢優勢という具合だ。
そして10年前は馬鹿にされていた技術も、もはや「安かろう悪かろう」のレベルではない。カメラはiPhoneに匹敵し、バッテリーに関しては凌駕する機種も。独自プロセッサすら開発している。
この10年で一体何が起きたのか?
中国企業は最初、「組み立て屋」だった。部品は全部外国製だった。
しかし、14億人の巨大な国内市場で利益を確保し、その金で技術開発を進めた。そして、技術が十分に育ってから世界展開したのだ。
2万円台のスマホが教えてくれること
中国製スマホの実力についてだが、最近私の妻がサブ機としてシャオミのスマホを楽天市場で買った。値段は新品で2万円台だった。
使ってみて驚いた。
5G対応。きれいな画面で速さも全く問題なし。長持ちするバッテリーに必要十分なカメラ。不満なのは全体的に大きすぎることくらいだが、これとて好みの問題だ。
「とても2万円台で買えるスマホとは思えない」
これが、中国メーカーの破壊力だ。そして、これは「K字型消費」の現在で圧倒的な強みとなる。
富裕層 ↗️ (プレミアム消費)
/
消費 ━━
\
中間層・低所得層 ↘️ (節約志向)金持ちは15万円のiPhoneやGalaxyを買う。品質、ブランド、ステータス、すべてが重要だ。
しかし、私のような貧困層~中流層は、それなりのスペックでできるだけ安いスマホを探す。そして、その機種にある程度満足している。
8〜10万円の「普通のスマホ」を買う人が減っている。格差が拡大している現在において、この流れは加速度的に進んでいくだろう。
AI市場も同じになる?
これらのスマホの事例はAI市場にも当てはまるだろうか?
では、2030年代を想像してみよう。
グーグルやOpenAI、先端研究機関は、今後も数万ドルのエヌビディア最新チップを買い続ける。おそらく他に選択肢はないだろう。
しかし、世界の数百万の中小企業、数十億の個人にとって、「80%の性能で30%安い」中国製は魅力的だ。そして、人数で見れば後者の方が圧倒的に多い。
さらに重要なのは世界の人口分布だ。市場は二極化している。
- 「最高」を求める人:欧米・日韓の10〜15億人
- 「そこそこで十分」な人:中国14億人+途上国50億人以上
中国は既にアフリカにITインフラを提供し、デジタルシルクロードを作っている。
AI時代には、この基盤を活かして、安い中国製AIチップ、中国製サービスを途上国に提供し、影響力を拡大するだろう。
このように、理屈的にはスマホ市場同様、AI市場も同じ構造になるかもしれない。
ただし、一つ大きな違いがある。それは前述のCUDAという要塞だ。
この20年かけて作られた開発環境は想像以上に強固だ。ファーウェイも代替システムを作っているが、10年後にもおそらくCUDAと同じレベルにはなっていないと思う。
だから、最先端のAI研究ではエヌビディアが必要であり続けるだろう。
しかし、「そこそこの性能」と「圧倒的な価格差」で、中国AIチップが市場を席巻する可能性は十分にある。
技術的には二番手。しかし市場では互角。これが、中国の現実的な到達点だ。
まとめ:冷静に、しかし油断なく
では、まとめよう。
個人的には、中国AI脅威論は過大評価されていると思う。
中国にとって、ソフト、メモリ、製造装置、地政学的孤立という4つの壁は高く、克服は極めて困難だ。
しかし、それは中国がこれからも無力で無害だ、という意味ではない。
10年前、誰が中国スマホメーカーが高い技術と圧倒的な価格差で世界シェア40%を握ると予測できただろうか。
しかし、それは現実になった。
もし、中国が国内市場で「実用レベル」を達成すれば、そこから先は加速する。K字型消費の時代、「下側の巨大市場」を支配することで実質的な勝者になる可能性は十分にある。
技術的に最高であることと、市場を支配することは、もはや同じではないのだ。
歴史は繰り返さないが韻を踏む。中国スマホが踏んだ韻をAI市場も踏もうとしているのかもしれない。