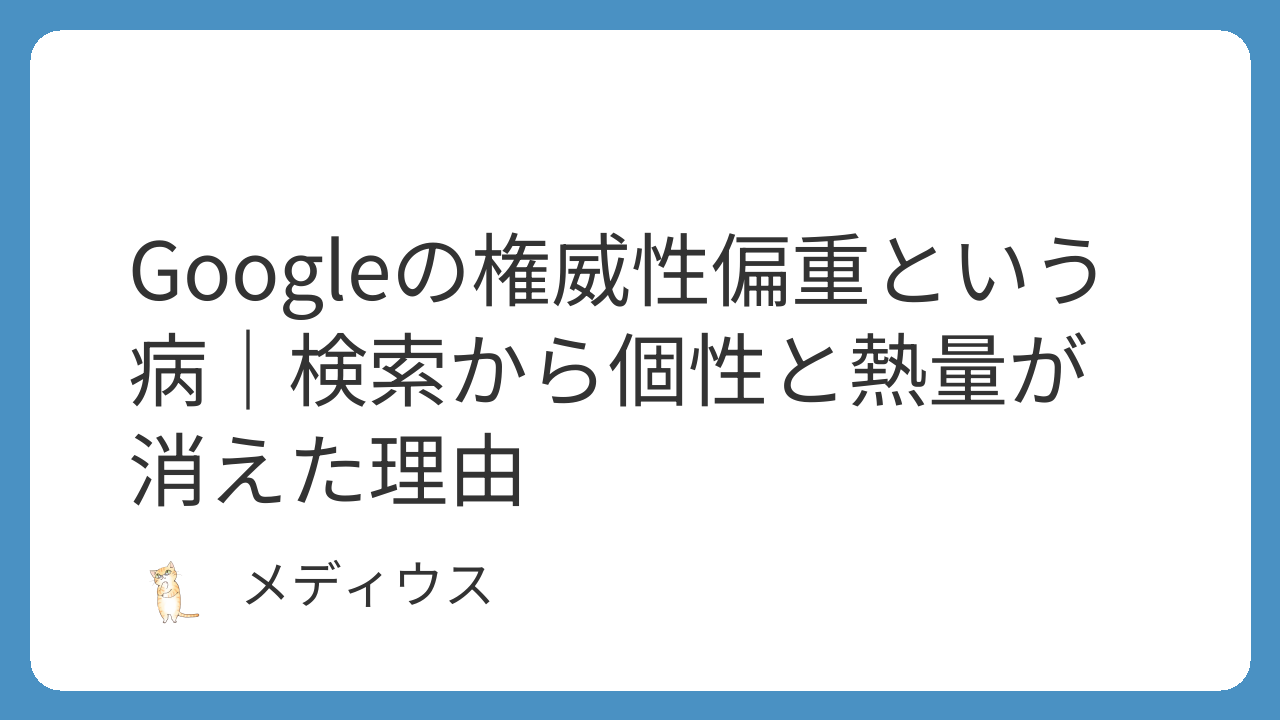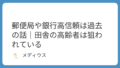2018-2019:Googleの検閲とダブルスタンダード
医療・健康ジャンルは権威性のみ重視の検閲状態に
2018年4月、私は「医療や健康の検索結果がゴミ化している」という記事を書いた。
DeNAのWELQ問題を受け、Googleは医療・健康関連の検索結果を大掃除した。まとめサイトの排除は歓迎すべきだったが、問題はその後だ。国内外の研究を分かりやすく解説していた良質な個人サイトまで一律で検索圏外に追いやられた。
Googleが選んだ道は、記事の質を見抜く努力を放棄し、とりあえず権威あるサイトだけ表示しておけばいいという安易な方針、すなわち事実上の検閲だった。
趣味・娯楽ジャンルの熱量喪失
そして、2019年4月の大規模コアアップデートは、その方針を日常生活の隅々にまで浸透させた。
プロ野球の試合結果を検索しても、表示されるのは共同通信の3行記事を転載した新聞社のコピペコンテンツばかり。熱量の高い個人野球ブロガーの詳細な試合感想はどこにもない。人の生命や財産に関わらないジャンルでさえ、Googleは「誰が書いたか(権威性)」を最優先したのだ。

Googleが最も嫌うはずのコピーコンテンツが、新聞社という「権威の衣」をまとった途端、無条件に上位表示される。これこそが、Googleのアルゴリズムにおける明白なダブルスタンダードである。
それから7年:何が変わったのか
あれから7年が経過した。Google検索は改善したのだろうか?
結論から言えば、改善していない。むしろ、新たな問題が加わり、利用者にとってさらに不便なものになりつつある。
Googleのシェアは変わらない
まず確認しておきたいのは、Googleの検索エンジンシェアは依然として圧倒的だということだ。
2025年現在、日本ではGoogleが約75〜80%のシェアを保持している。スマートフォンに限れば90%を超える。Yahoo!は約10%、Bingは約10%程度で、この状況は2018年からほとんど変わっていない。
つまり、Google検索の品質がどうであれ、ほとんどの日本人はGoogleを使わざるを得ないのだ。
「何を言ったか」ではなく「誰が言ったか」が全て
2018年のアップデート以降、Googleは「E-A-T(専門性・権威性・信頼性)」を重視するようになった。そして2022年には「E-E-A-T(Experience:経験を追加)」に進化したと発表した。
建前上は「経験」も評価するという。しかし実際には、依然として「権威性」が最優先されている。個人が実際に体験して書いた熱量の高い記事よりも、大学や企業が形式的に書いた無難な記事が上位に来る。
「何を言ったか」ではなく「誰が言ったか」が評価の全てだ。私が2018年に批判した状況は、7年経っても全く改善していない。
スパムサイトの巧妙な「権威性偽装」
さらに厄介なのは、スパムサイトがGoogleのアルゴリズムを逆手に取り、巧妙に進化したことだ。
2025年のスパム業者は、もはや露骨なアフィリエイトサイトではない。彼らは会社概要、特定商取引法に基づく表記といった形式的な「権威性の体裁」を完全に整え、あたかも信頼できるECサイトであるかのように偽装する。
これらの外見だけの権威は、真に有益な情報を持つ個人サイトを押し退け、検索上位に表示され続けている。
AI生成記事の氾濫と検索結果の無個性化
そして2023年以降、さらに深刻な問題が加わった。AI生成コンテンツの大量流入だ。
ChatGPTをはじめとする生成AIの登場により、誰でも簡単に大量の記事を生成できるようになった。その結果、検索結果はそれらしい文章で埋め尽くされるようになった。
これらのAI生成記事には共通の特徴がある。一見まともに見えるが、実体験がゼロ。当たり障りのない内容で、誰が読んでも同じ。個性がなく、熱量もない。まるで教科書の劣化コピーのような文章だ。
Googleは「AI生成コンテンツは禁止しない」という立場を取っている。つまり、AI生成記事もコンテンツの質で評価するという建前だ。しかし実際には、AI生成記事が検索上位を占めるケースが増えている。
なぜか。答えは簡単だ。AI生成記事は「無難」だからだ。間違ったことを書かない。誰も傷つけない。リスクがない。Googleのアルゴリズムが求める安全なコンテンツに完璧に合致している。
一方で、個人が実体験をもとに書いた記事はリスクがあると判断される。主観的すぎる、偏りがある、権威性がない、そんな理由で順位を落とされる。
結果として、検索結果は「無難で無個性なAI記事」と「権威はあるが面白くない公式サイト」で埋め尽くされている。
若年層の検索離れ
こうした状況を受けて、若年層を中心にGoogle検索離れが起きている。
彼らはGoogle検索を信用していない。代わりにX、Instagram、TikTokで情報を検索する。ハッシュタグ検索やアカウント検索で、リアルタイムの生の声を拾う。また、ChatGPTやPerplexityなどのAI検索を使う人も増えている。How系の質問にはAI検索の方が効率的だからだ。
ただし、日本ではまだこれらの代替手段は補完的な位置づけだ。完全にGoogle検索を置き換えるまでには至っていない。Googleの独占状態は続いている。
真面目なブロガーが消えていく
そして、最も深刻な問題がこれだ。
真面目にオリジナルで価値ある記事を執筆しようとしているブロガーのやる気を、Googleは完全にそいでいる。
どんなに時間をかけて調査し、どんなに実体験をもとに丁寧に書いても、検索結果では権威あるサイトやAI生成記事、スパム・詐欺サイトにすら負ける。何ヶ月も何年もかけて育ててきたブログが、ある日突然のアップデートで検索圏外に飛ばされる。理由も分からない。修正しても戻らない。
こんな状況で誰が真面目に記事を書こうと思うだろうか。実際、多くの個人ブロガーがブログをやめている。「もうGoogleのアルゴリズムに振り回されるのは疲れた」「どうせ評価されないなら書く意味がない」そんな声をよく聞く。
これは単にブロガー個人の問題ではない。インターネット全体の情報の質の問題だ。真面目な個人ブロガーの消失、それはつまりインターネットから「個性」と「熱量」と「実体験」が消えるということだ。
白河の清きに魚も住みかねて
2019年、私はGoogleにこの狂歌を送った。
江戸時代の老中、松平定信(白河藩主)は賄賂政治で有名な田沼意次の後を継ぎ、厳しい改革(寛政の改革)を行った。しかしあまりに厳格すぎて庶民は苦しみ、「清廉潔白すぎて息苦しい。賄賂まみれでも自由だった田沼の時代が恋しい」と皮肉られた。
Googleがやっていることは、まさにこれだ。検索結果をクリーンにしようとして、権威あるサイトだけを表示する。しかしその結果、検索結果は無難で面白くないものばかりになった。アルゴリズムを悪用する詐欺サイトには寛容な分、なおさらたちが悪い。
これがあの時からずっと変わらないGoogle検索の姿だ。
まとめ:私たちにできることは何か
では、私たちユーザーにできることは何か。
一つは、Google以外の検索手段を併用することだ。X(Twitter)でのハッシュタグ検索、AI検索、Redditでの情報収集(英語ができれば)。完全にGoogleを捨てることはできないが、依存度を下げることはできる。
もう一つは、良質な個人ブログを見つけたら、ブックマークし、RSSリーダーに登録し、直接訪問することだ。Google検索に頼らず、直接その情報源にアクセスする。
そして最も重要なのは、真面目に記事を書いているブロガーを応援することだ。コメントを残す、SNSでシェアする、note等で直接支援する。Googleが評価しないなら、私たちが直接評価すればいい。
何度でも言う。インターネットはGoogleのものではない。私たちユーザーのものだ。