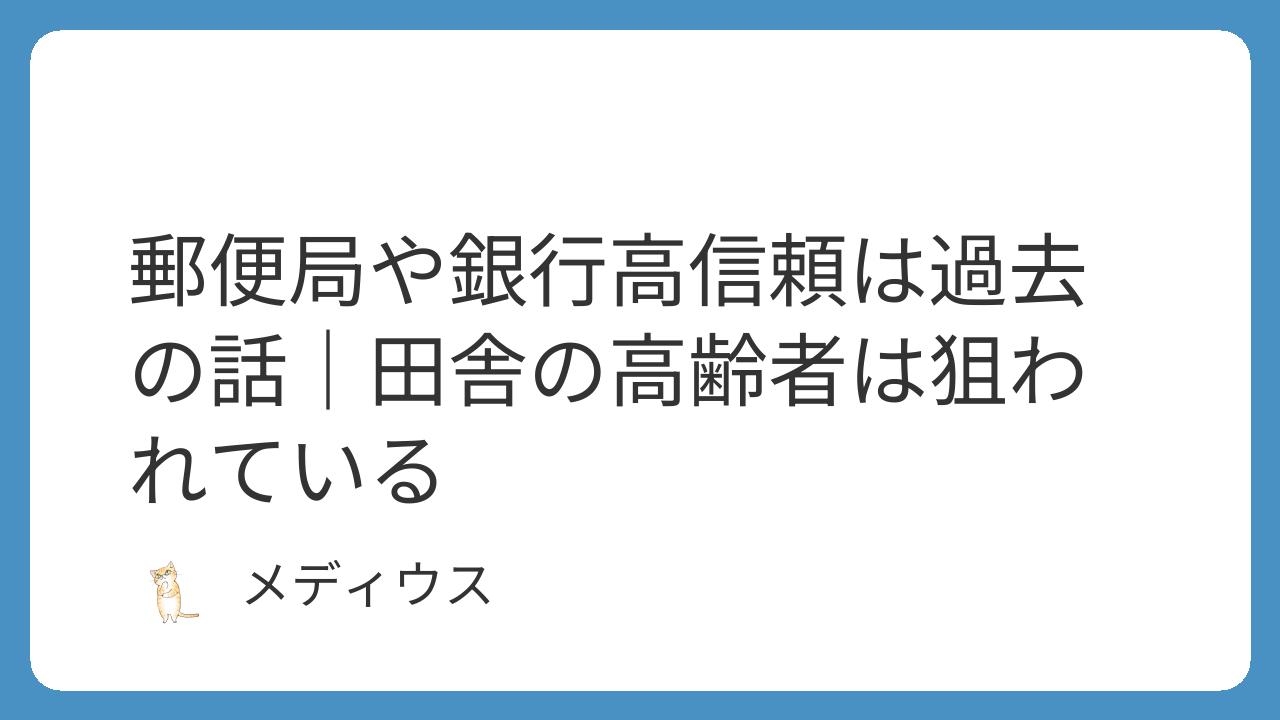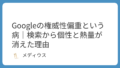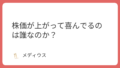2019年、かんぽ生命問題が明るみに出た
2019年6月、かんぽ生命保険の不適切販売問題が発覚した。
福岡県の70代女性が、郵便局員に強く勧められて保険を乗り換えたところ、月額保険料が3万円以上増え、不要な特約まで勝手に付けられていた。
この問題は氷山の一角だった。全国で18万3000件もの不適切契約が確認され、日本郵政グループは業務停止命令を受けた。
参考:「納得できない」かんぽ生命、乗り換えで月3万円増 70代女性憤り 不適切営業問題
私の母も被害者だった
同じ頃、我が家でも似たような事があった。
年金暮らしの母が郵便局に毎月数万円ずつ貯金をしていたところ、郵便局員から「それだけ毎月貯金するなら貯金代わりに半分くらいうちの保険にも入ってください」と言われ、保険に加入したのだ。
母は「お金が増える」と思って加入したが、実際には支払った保険料に遠く及ばない解約返戻金しかない保険設計だった。必要のない入院特約も勝手に付けられていた。すぐに解約を申し出たが、母に理由を聞くと印象的な答えが返ってきた。
「いつも行っている郵便局なので断れば今後嫌な対応をされるかもしれないと思った」
「郵便局は昔からあるので信用できると思っていて、損な事を勧めるはずはないと思った」
母は昔から「郵便局や銀行の人はしっかりしている」と口癖のように言っていた。都会の人からすれば「はぁ?」という話かもしれないが、田舎では年寄りを中心に未だに郵便局や銀行を正義の味方のように思っている節があるのだ。この「信頼」こそが、彼らにとって最大の武器になっている。
それから6年:何が変わったのか
2019年の問題発覚後、かんぽ生命は業務停止命令を受け、不適切契約の調査と返金対応、営業体制の見直しを行った。しかし、問題の本質は変わっていない。
2023年、再び不適切販売が発覚
かんぽ生命は2023年にも、顧客に不利益となる保険の乗り換え契約が新たに見つかったと発表した。2019年の問題発覚後も、不適切販売は続いていたのだ。
なぜ繰り返されるのか?それは、郵便局員に課せられた「ノルマ」が変わっていないからだ。処分や謝罪だけでは、構造は変わらない。
地方銀行の「必死さ」はさらに増している
2019年当時、日銀は「地銀の6割が10年後赤字転落」という試算を出していた。あれから6年、地銀の経営環境はさらに厳しくなっている。
地銀の現状(2025年)
- 低金利政策の長期化で貸出業務では稼げない
- 人口減少で地方経済が縮小
- デジタル化で店舗維持コストが重荷に
- 統廃合が進むも収益改善せず
統廃合も進んだ。2019年の地銀106行が、2024年には62行まで減少した。44行も減ったのだ。しかし統廃合しても、収益構造は変わらない。本業で稼げない分、手数料ビジネスに依存するしかないのだ。
銀行が高齢者に売りつける商品は時代とともに変わってきた。
投資信託は手数料競争で旨みが減少し、次は生命保険、そして今は外貨建て保険や仕組債だ。次から次へと、「売れば儲かる商品」を高齢者に売りつけている。
参考:まさか銀行がダマすわけが…あった!大損する被害続出、この保険商品を買ってはいけません
株主資本主義の加速:客より株主が優先される時代
ここからが、2019年と2025年の最大の違いだ。
2014年以降、日本企業は「稼ぐ力」の強化を求められてきた。特に2023年の東証の要請以降、PBR1倍割れ企業への株価是正圧力が強まっている。
日本株への海外投資家の投資が活発化し、地銀や日本郵政のような金融株にも海外資本が入ってきている。彼らが求めるのはROE(自己資本利益率)の向上、配当性向の引き上げ、自社株買いだ。つまり、株主への還元を最優先しろということだ。
日本郵政は2015年に上場した。それ以降、株主への説明責任が発生している。ユニバーサルサービスを維持しながら利益を出さなければならない。そのプレッシャーは、現場の郵便局員に「ノルマ」として降りてくる。
地銀も同じだ。経営が苦しい地銀ほど、株主から「配当を維持しろ」「収益を上げろ」とプレッシャーを受ける。本業で稼げないなら、手数料ビジネスで稼ぐしかない。その結果、現場には厳しいノルマが課せられる。
悪循環の構造はこうだ。
株主の圧力が増大し、収益目標が引き上げられる。現場へのノルマが強化され、不適切販売の温床となる。慈善事業ではなく株式会社である以上、郵便局も銀行も株主に利益を還元しなければならない。そのしわ寄せが最も抵抗力の弱い田舎の高齢者に向かっているのだ。
田舎特有の「断りにくさ」は変わっていない
都会では、銀行や郵便局の担当者と顔を合わせる機会は少ない。しかし田舎では違う。
郵便局や銀行は地域に1つか2つしかない。担当者と顔なじみになり、断れば今後の関係が気まずくなる。「お世話になっている」という意識が強い。私の母が「断れば今後嫌な対応をされるかもしれない」と思ったのは、この構造があるからだ。
コミュニティが狭い分、より断りにくい。そして、田舎ではデジタル化が進まず、対面営業が主流のままだ。高齢者はネット銀行やネット証券を使わない。結局、地元の郵便局や銀行に頼るしかない。
彼らはそれを知っている。だから、田舎の高齢者は格好のターゲットになる。
新たな手口:さらに巧妙化している
2019年当時は「保険の転換」が問題だったが、2025年には新しい手口も登場している。
外貨建て保険は「円安で資産が目減りする。今のうちに外貨建て保険で資産を守りましょう」と勧められる。為替リスクの説明が不十分なまま販売され、円高になった時に大損するケースが続出している。
仕組債は「定期預金より利回りが良い。元本保証ではないが、よほどのことがない限り大丈夫」と説明される。実際には複雑な金融商品で、株価が一定水準を下回ると大損する。高齢者には理解できない商品だ。
相続対策の保険は「相続税対策になる。今のうちに孫に保険をかけておけば節税になる」と勧められる。実際には節税効果はほとんどなく、解約すれば大損する保険だ。
投資信託の乗り換えも横行している。「今の投信は運用成績が悪い。もっと良い投信に乗り換えましょう」と言われる。実際には手数料を稼ぐためだけの乗り換えで、乗り換えるたびに手数料が取られ、顧客は損をする。
田舎の高齢者を守る方法
私のように高齢の両親を持つ人は、最大限の注意を払ってほしい。
定期的に両親の契約をチェックしよう。保険証券、銀行の通帳、証券会社の取引報告書を確認する。「貯金のつもりで入った」という保険は要注意だ。解約返戻金が支払保険料を下回るなら、それは貯金ではない。
「相続税対策」「節税」という言葉には要注意。本当に節税効果があるのか、税理士に確認する。外貨建て保険や仕組債は原則買わない。高齢者には理解できない商品は買わせない。
「今日中に契約を」と急かされたら断る。本当に良い商品なら、明日でも買える。
もし不適切な契約をしてしまったら、すぐに解約を申し出る。クーリングオフ期間内なら無条件解約可能だ。金融庁や消費生活センターに相談する。悪質な場合は弁護士に相談する。
まとめ
元記事執筆から6年経っても私の考えは同じだ。
郵便局や銀行が信頼できる存在というのは過去の話。今は騙しやすい人間を騙して利益を上げようとする輩が跋扈する時代であり、それは郵便局や銀行も例外ではない。いや、むしろ彼らは「信頼」という武器を持っているからこそ、より危険なのだ。
慈善事業ではなく株式会社である以上、郵便局も銀行も株主に利益を還元しなければならない。その圧力は今後も強まる。海外投資家の増加、コーポレートガバナンス改革、PBR是正要請。すべてが「もっと稼げ」というメッセージだ。そのしわ寄せは、今後も最も抵抗力の弱い田舎の高齢者に向かうだろう。
私たちにできることは、身近な高齢者を見守り、不適切な契約から守ることだ。この記事が、誰かの役に立つことを願っている。